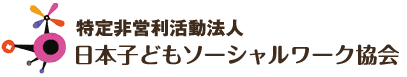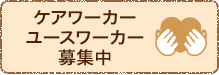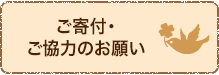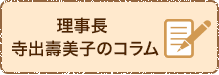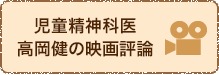帰途に残る哀感:「止められるか、俺たちを」
Vol.42 更新:2018年11月6日
▼若松組の内部にいた人や、きわめて近縁に位置していた人たち、あるいは喧嘩別れした人々を別にするなら、「止められるか、俺たちを」(白石和彌監督)は、かけねなしに楽しめる映画だ。加えて、観終ったあとの帰途に、大きくも小さくもない哀感が残る。この哀感は、どうにも棄てがたいものだ。
▼新宿でフーテンをしていた吉積めぐみ(門脇麦)は、女子高生に見える知り合いはいないかと尋ねられたことをきっかけに、若松プロでピンク映画の助監督を目指すことになった。原宿のセントラルアパートにある若松プロには、若松孝二(井浦新)のほか、足立正生(山本浩司)、高間賢治(伊島空)、福間健二(外山将平)らが出入りし、議論をたたかわせながら、映画を量産している。他にも、大島渚(高岡蒼佑)や大和屋竺(大西信満)らが登場する。めぐみは、助監督としては頭角をあらわすが、ラブホ向けの初監督作品では、失敗してしまう。「赤軍−PFLP世界戦争宣言」を撮った足立は、「赤バス」を仕立てて全国を回り、送り出す若松は、勇ましい言葉とは裏腹に、小銭を渡すにもしぶしぶという気持ちが明らかだ。一方、めぐみは妊娠したが、それを誰もが知らないまま、自殺とも事故ともつかぬ形で命を絶った――。
▼このようなメインストーリー以外にも、観客に対するある種のサービスなのだろうが、若くして自殺した長沢延子の本や、後に連合赤軍事件で亡くなった遠山美枝子がオニギリ一つ握れないと若松から揶揄されるシーン、後の日本赤軍の活動家=和光晴生のアルバイトシーンなども、随所に登場する。おまけに(といっては語弊があるが)、オリジナル(らしい)歌が、カルメン・マキを髣髴とさせる形で挟み込まれている。
▼この映画の特徴を、一つあげろと言われれば、何よりもセリフにオーバーラップする音楽が、セリフの中味をやや聴き取りにくくする程度の音量にまで、上げられている点だと答えるだろう。その結果、セリフの内容は第二義的な意味しかもたなくなり、会話のやりとりに伴う雰囲気だけが、第一義的重要性をもつことになる。
▼私のように、それほど熱心な若松ファンではない者の記憶でさえ、容易に喚起されるように、「汚された白衣」などの有名シーンが、冒頭から散りばめられている。また、撮影風景やダビングの風景といった形で、再現されている作品も多い。「女学生ゲリラ」、「処女ゲバゲバ」などだ。付け加えるなら、めぐみは、「め組」という印象深い名前でクレジットされていたことが、私などの記憶には残っているが、その表記も登場する。
▼めぐみは、生きていたなら、映画の世界か全く別の世界においてかはわからないが、大成していたかもしれない。あるいは、一切の舞台から降りて、平凡な生活を営んでいたかもしれない。どちらであってもいいから、幸せな人生を全うしてほしかった。そういう気持ちにさせられることによって、冒頭に記した哀感が、私たちの中に生じる。