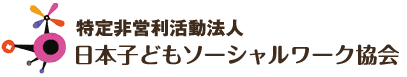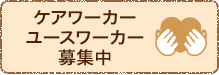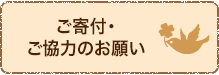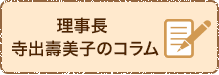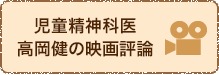結果としてのストリートアート:「バンクシーを盗んだ男」
Vol.40 更新:2018年9月11日
▼ドキュメンタリー映画「バンクシーを盗んだ男」(マルコ・プロゼルピオ監督)は、ニューヨークにおける消費資本主義と、パレスチナにおける資本の原始的蓄積(あるいは粗野な経済衝動)が、非対称的だという当然の事実を、改めて鮮明な形で見せてくれた。
▼ニューヨークの資本主義の下でのバンクシーに関しては、私たちは映画「バンクシー・ダズ・ニューヨーク」を通じて、すでによく知っている。(本連載Vol.14「プロセスとしてのストリートアート」を参照してください。)ニューヨークの住民は、2013年に、バンクシーによるストリートアートを堪能した。それは、エコロジストのキャンペーンに堕することを、ぎりぎりのところで回避していた。また、その映画の中でインタヴューに答える女性は、好意的な言い方で、「バンクシーは裏で許可をとっていて、法に触れない線を確保しているのでは」と語っていた。総じて、資本主義社会に暮らす人々が共通して抱く、ある水準の生活思想を、手慣れた技法で切り取るツボを押さえている点で、バンクシーはエコロジーアーチストとは根本的に異なっていた――。
▼一方、「バンクシーを盗んだ男」では、ニューヨークの資本主義は後景へ追いやられ、ヨルダン川西岸の分離壁に描かれたバンクシーの作品「ロバと兵士」が、巨大なカッターで切り出される。そして、デンマークからロンドンを経て、ロサンゼルスのオークションハウスへと送られる。しかし、結局は売れ残ってしまう。映画の中では、バンクシーを称え高く評価する西洋女性の意見が、皮肉か揶揄であるかのように挟み込まれるが、主調音は、パレスチナのタクシードライバーであるワリドの声によって奏でられる。
▼ワリドは、彼の雇用主に、バンクシーの作品を壁から切り取って売り払うことを提案し、自ら実行するが、報酬を手にすることが全く出来なかった。彼は、バンクシーの思想や行動を批判するが、作品を批判しているシーンはない。作品自体には、ほとんど関心を抱いていないからだ。
▼結局、この映画の観客としての私は、ワリドの主張を含めて、パレスチナのバンクシーを愉しむことが出来たかどうか。そこは不確かなところだ。さすがに「裏で許可」はとっていないだろうが、法に触れても触れなくても安全な線を、バンクシーが確保していることは間違いない。バリドは、そこが我慢ならないのだろう。このとき、バンクシーは、パレスチナの人々が共通して抱く、ある水準の生活思想を切り取っていないことになる。だから、作品はワリドの関心の外に排除され、思想と行動のみが軽い憎悪の対象になる。
▼換言するなら、プロセスとしてではなく結果としてのストリートアートが、パレスチナには存在するだけだ。他方、バンクシーが分離壁のすぐ横に開業したという「The Walled Off Hotel」は、顧客にとってもホテルマンにとっても、予約から宿泊を経て土産話に至るまでの、すべてがプロセスだ。その場所ならば、消費資本主義の価格形成が可能になる。