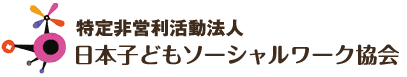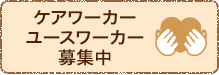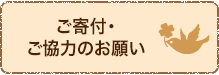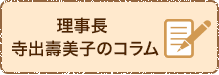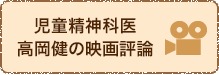天上と地上との境界:「海辺の生と死」
Vol.33 更新:2017年8月7日
▼梯久美子・著『狂うひと―「死の棘」の妻・島尾ミホ』は、衝撃的な本だった。それまで、吉本隆明や奥野健男によって確立されたかにみえた、貴種としての特攻隊長=島尾敏雄と、古い神話的共同性の枠組みを象徴する「少女」=ミホとの邂逅という解釈を、この本が崩し去ったからだ。(ついこのあいだ読んだ本なのに、探してもみつからないから、不確かな記憶だけで書くが、)「一方的に小説に書かれる人」と思われてきたミホが「書く人」でもあったこと、また、「書く人」=島尾敏雄の女性問題が、小説を書く目的のために故意に引き起こされた節があることなどを、敏雄やミホ自筆の膨大なメモ類を駆使して論証していった同書は、いわばドキュメンタリーの恐ろしさを、読者に思い知らせたといっても過言ではなかった。
▼映画「海辺の生と死」(越川道夫監督)は、かなりの程度で梯の本を意識しながら、つくられているようだ。ミホは、映画では、島尾敏雄の短編「島の果て」と同じくトエという名前で、南島の言葉を駆使しうる満島ひかりが演じている。(敏雄は、やはり「島の果て」で使われた朔中尉という名前で登場し、永山絢斗が演じている。)トエの出自は奄美ではなく、どこかから養子として奄美の名家にもらわれてきて、ある時期には婚約者もいた。このあたりは、島尾敏雄の小説では、「トエはいくつになるのか誰もしらなかった」「二、三の年寄りたちは、トエがこの部落の生れの者でないことを知って居りました」というように、ぼかして記されている部分であり、梯の本を積極的に参照することにより、はじめてこのような設定が可能になったのだろう。
▼ところで、映画の中で、もっとも私の印象に残ったのは、死の使いである梟を、暗緑色の森の中で追い払う場面だった。こういう伝承が実際に奄美にあるのかどうか知らないが、島尾ミホの作品(「鳥九題」)には、夫(敏雄)は梟の鳴く声を聞くと心が和むというが、私(ミホ)は反対に心が黒い霧に閉ざされるような重苦しい気持ちになると、記された部分がある。海の向こうからやってきた貴種である島尾敏雄と、神話的共同性を体現するミホとの違いを、ミホ自身が記したと、とれなくもない。
▼映画の原作と思われる島尾ミホの作品は、同名の短編集に収録された「その夜」だが、そこにも「ティコホー、ティコホー」という梟の声を聞いた私(ミホ)が、「隊長さま(島尾敏雄)や私が死んでしまった後でも、やはりこうして啼いているのでしょう」と感じる箇所がある。梟を追い払う伝承を描いたことで、映画は、梯の解釈を援用しながらも、貴種―神話的共同体、つまり天上と地上との境界という構図を、根幹のところで残した。そして、そのことにより、この映画は、島尾ミホの著作と、視点が合致したのではないか。こうみてくるなら、映画の中の玉音放送の場面(島尾敏雄の小説「出発は遂に訪れず」にはあるが、島尾ミホの「その夜」にはない)は、不要のような気がした。