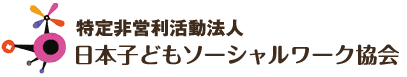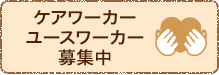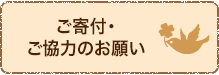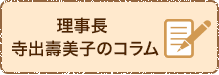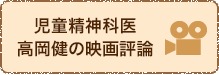新しいワーキング・クラス・フィルム:「未来を花束にして」
Vol.30 更新:2017年4月12日
▼イギリスの歴史に取材した映画というと、大河ドラマ風の文芸作品が、まず頭に浮かぶ。一方で、ワーキング・クラスを描いた映画だと、閉山した炭坑や弱体化した労組などを背景にする、ユーモアとペーソスあふれる秀作が、いくつか思いつく。だが、それらのいずれでもない、ワーキング・クラスの歴史映画が、ついに登場した。「未来を花束にして」(サラ・ガヴロン監督)が、それだ。冴えない邦題に騙され、期待しないで観にいくと、良い意味で裏切られることになる。
▼原題を「SUFFRAGETTE」という。エンゲルスが「イギリスにおける労働者階級の状態」を著してから60数年後、ロシア革命直前の頃のロンドンで闘われていた、女性参政権運動を指す言葉だ。それも、生半可な運動ではない。商店のガラスを割る。郵便ポストに放火する。果ては、ロイド・ジョージ蔵相の別荘を爆破する。そして、捕えられると、獄中でハンガーストライキを決行する。
▼これらが、くすんだ灰色を基調とする街と建物の内部で、展開されるのだ。照度を抑えた画面には、花や衣服の青紫色が、点景のように嵌めこまれている。そこを、帽子をかぶり、コートのポケットに手を入れて、さっそうと歩く女性活動家がいる。
▼洗濯工場の女性労働者モード(キャリー・マリガン)は、下院の公聴会で、思いがけず証言をすることになった。証言後、自分の言葉が、ロイド・ジョージら政治家の耳に達したと満足していた彼女は、そうではなかったことを知った。リーダーのパンクハースト夫人(メリル・ストリープ)の演説に影響を受け、活動に参入した彼女は、夫に家から追い出され、息子と会うことすらできず、しかも工場を解雇されてしまう。
▼モードの行動は、観客をして、心の中で快哉を叫ばせるに十分だ。解雇時には、工場長の手の甲に、熱せられたアイロンを一瞬のうちに押し当てて、去っていく。また、映画の終盤近くでは、工場の女性同僚の娘を、これもあっという間に児童労働の場から外へ、連れ出してしまう。ちょうど、自分から奪われ養子にやられた我が子を、取り戻すかのようにだ。しかも、これらの行動が、さっそうとした歩行のテンポと、同期している。
▼このあたりが、前回とりあげた「母」などとは、全く違うところだ。モードという女性は架空の人物だというが、時代背景としては、日本の小林セキが幼い多喜二を育てている頃と、おおよそ同じだ。優劣を言い立てるつもりはないが、モードが受けた(受けてこなかった)教育の水準と、タキの教育の水準とのあいだに、それほどの違いはなさそうだ。すると、両者の違いは、英日の歴史と風土の違いに根ざすというしか、ないのかもしれない。
▼また、ワーキング・クラスばかりでなく、それに先行するプチ・ブルジョアジーの運動を比べた場合でも、パンクハースト夫人と平塚らいてうのあいだには、30数年の径庭があり、それは女性参政権の実現年についての彼我の差と、ほぼ同じ年月だった。