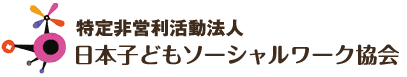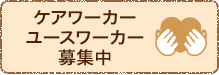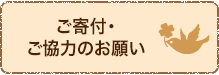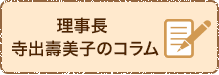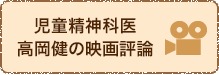ためになる娯楽映画:「ブリッジ・オブ・スパイ」
Vol.19 更新:2016年3月23日
▼話題作「ブリッジ・オブ・スパイ」(スティーヴン・スピルバーグ監督)を観た。この作品を含めて、スピルバーグが監督ないし製作した戦争映画の特質を一言で表すなら、「ためになる娯楽映画」といったあたりに落ち着くと思う。「娯楽映画」として一級品であることについては、説明が不要だろう。一方、「ためになる」に関しては、少し説明が要るかもしれない。
▼まず、「プライベート・ライアン」でも「硫黄島からの手紙」でもいいが、こういう史実があったのかと啓発される場面が、随所に挟み込まれている。もっとも、正確にそのとおりなのかという疑問を抱いてしまうと、一観客としては簡単に検証できるわけではないから、どこかで打ち止めにして「娯楽」へ回帰するしかなくなる。逆にいえば、観客なりに掘り下げようとしても壁に跳ね返されてしまうことをわかった上で、その範囲内で物識りになることが出来るだけだ。だから、啓発された内容をそのまま自慢げに語ると恥ずかしい。
▼次に、反戦を主張している気分にしてくれるが、それを観客が徹底しようとしても、途切れてしまい長続きしない。つまり、反戦は錯覚で、ちゃんとエクスキューズが仕込まれている。星条旗への忠誠が基盤ですよという解釈が、どこからでも容易に取り出しうる仕掛けになっているのだ。そういうわけで、史実や反戦は、いわば金持ちの教養言説にとどめおいて、愉しみに徹するしかない。それが、「ためになる娯楽映画」の意味だ。
▼「ブリッジ・オブ・スパイ」も例外ではない。1957年、ソ連のスパイだとして、アベル(マーク・ライランス)という男が逮捕された。国選弁護人になったのは、かつてニュルンベルク裁判で検察官をつとめ、今は保険金の交渉を専門とする、民間人のドノヴァン弁護士(トム・ハンクス)だった。彼は、民衆から冷たい視線を浴びながらもアベルの死刑を回避し、東ベルリンへ赴いて、ソ連に拘束されているスパイ・パイロットのパワーズおよびアメリカ人学生プライヤーとの、1対2の交換に成功する。
▼冷戦下で行われた米ソ間のスパイ交換のエピソードも、映画では最後の字幕でしか扱われていないキューバ侵攻に伴う捕虜の解放交渉も、多少は耳にした記憶があるから、フィクションでないことはわかる。しかし、映画の冒頭にinspired by true eventsと記されていることからは、かなり脚色されていると割り切って観るしかない。
▼また、スパイ交換の成功が、結果的に米ソ間の全面戦争を回避することにつながったといえないこともないが、弁護士ドノヴァンの思想は、反戦ではない。アイリッシュ・アメリカンもジャーマン・アメリカンも共存しうるのは、アメリカに法があるからだという一点に収斂してしまうだけで、そこからは深まらない。アメリカ社会の教養とは、昔も今も、この程度のものだ。そういう、誰もが気づいている事実を再確認しながら愉しむ映画が、スピルバーグの作品だ。