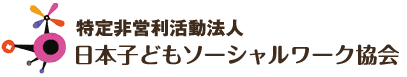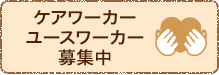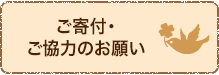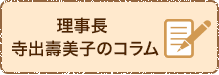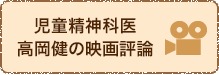アイデンティティ・ポリティクスに回収されない男女の記憶:「ゴールド」
Vol.113 更新:2026年2月9日
▼自分なりに上昇したいのに、制度のため出来ないと感じている女がいる。反対に、降りたいのに、規範意識のため降りることは許されないと思い込んでいる男がいる。この図式は、たいていアイデンティティ・ポリティクスに回収されるだけだ。もし、どこかでこの図式を受け入れたくない気持ちがあるなら、そこからどこへ向かえば本当の生活へとつながるのか。こういう本質的な問いに答えようとした作品は、管見の限りでは、文学においても映画においても思いのほか少ない。
▼そういう数少ない作品の中の一つが、映画「ゴールド」(知多良監督)だ。イベント会社の事務職ミキ(小畑みなみ)は、会社で雑用を次々と振られ、帰り道に涙が出る。彼女は、途中下車した高円寺の閉まったシャッター前で、缶ビールを片手に路上ライブを聴いているとき、料理の得意な弘樹(サトウヒロキ)と出会い、一緒に暮らし始めた。ミキは、弘樹にはずっと家にいてほしかったが、弘樹は社員になろうとして清掃会社に就職する。だが、そこは隠微なパワハラが溢れる職場だった。一方、男女差別が横行していたミキの会社では、同僚女性の山中がミキからパワハラを受けたと訴えはじめた――。
▼ブルシット・ジョブというしかないにもかかわらず重要な仕事をしているつもりの上司や取引先の社員と、そこに埋もれてしまいがちな女性事務員の敵意が歪み、ミキへと向かっている。また、劣悪な労働条件で働く弘樹の職場では、エッセンシャルワーカー達のあいだで、鬱憤を弱者へ振り向ける形でのいじめが横行する。そんな状況が描かれる一方で、舌足らずだが精一杯背伸びした言葉を吐こうとするライブアーティストの女性とミキとの会話に、あずさと八川という脇役カップルが加わった場面は、予定調和のない思考を少しのユーモアで包みながら描いていた。たとえば、女性アーティストが話す「自由ってルールを知ること」という言葉の中の「ルール」とは、おそらく与えられた条件という意味であり、自由意志は存在しないという哲学者の言葉と対応しているのだろうが、そういう生煮えの会話の前後に、「世間じゃなくて私が言ってんの」「だし、彼にミキさんがこんなに大変なのを知ってもらうのも大切だと思うよ」というあずさの言葉が配置され、一瞬の安定感をもたらしている。
▼この映画には、「第1話 生活」や「第2話 ロマンス」といったテロップが挟み込まれている。第3話と第4話と第5話のテロップは、それぞれ再び「生活」「ロマンス」「生活」だ。つまり、生活とロマンスの往還の物語が、この映画ということになる。しかし、ロマンスという伝統的語りが似合う恋愛関係が維持されないであろうことは、男女の間で最初からうすうす予想がついていた。それでも、アイデンティティ・ポリティクスに回収されることのない、一筋の記憶だけは残る。そこを描いた映画は、必然的に観客の記憶にも残ることになった。