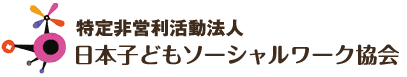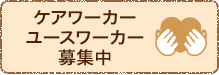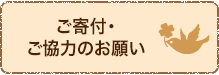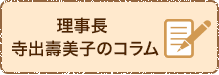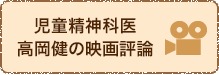現実を掠りとる言語と現実に搦めとられる言語:「旅と日々」
Vol.111 更新:2025年11月12日
▼つげ義春原作の映画に外れがないのはどうしてか。つげ漫画自体の面白さはもちろんとして、映画化にあたり監督の切り口が原作の細部から離れない(あるいは離れようにも離れられない)がゆえに、無用の用とでも呼ぶほかないものが常に描かれていること、そして版元がかわりながらも現在に至るまで漫画が何度も刊行されていることにより、観客が原作を繰り返し愛読して記憶していること。少なくとも、その二つが理由だと思う。
▼映画「旅と日々」(三宅唱監督)の前半は、つげの「海辺の叙景」を下敷きにしている。夏の海辺で、夏男(髙田万作)は渚(河合優実)と出会う。(ただし、原作にはどちらの固有名詞も出てこない。)二人は台風が近づく海で泳ぎ、渚は夏男を見て「いい感じよ」と呟く――。つげ作品の読者なら誰でも覚えている科白だが、原作では「いい感じよ」の前に「あなたすてきよ」という呟きがある。それが無くなったのは、おそらく現代にマッチしない科白と思われたからだろう。加えてもっとトリビアルな相違点をいえば、原作で煙草を吸うのは夏男だが、映画では渚だ。同様に、渚は、原作ではデザイナーかと問われて否定していないが、映画ではおよそデザイナーらしくない服をまとっている。(それにしても河合はどんな役でもできるのだなあと感心してしまう。)
▼さて、この前半部分は劇中劇で、その脚本を書いたのは李(シム・ウンギョン)という名前の女性だ。李はハングルでプロットを書いているが、思うように筆が進まない。そのため、「旅行にでも行くといい」との助言に従い、映画の後半で冬の北国へ出かけて、べん造(堤真一)という老人が一人で営む、囲炉裏以外には暖房のない宿に泊まる――。後半部分の下敷きになっているのは、つげの「ほんやら洞のべんさん」だ。この漫画を読んだことのある者なら必ず覚えているであろう科白(「べらべらとよく喋るね」)が映画でも使われていて、観客の笑いを誘う。
▼ところで、映画には、原作にない「言葉に搦めとられる」ことによる苦悩といった表現がみられる。だが、ほんとうは違うのではないか。つげ作品を念頭に置く限りは、言葉は最初から現実の外部に置かれている。そして、ほんの一瞬だけ現実を掠める構造になっている。「ほんやら洞」でいえば、映画にはない「とりッ!この鳥や」「スズメスズメすはどり立ちやかれ」といった、「べんさん」の元妻と暮らす子どもの意味不明の言葉がそれだ。しかし、映画では、「べんさん」と李が錦鯉を盗みに来たことを内緒にするよう子どもに言い聞かせる、ありふれた会話に置き換えられている。これは、搦めとられる言語だ。
▼映画には、錦鯉を盗みに忍び込んだ際、李がカメラを失くしてしまうシーンがある。中古カメラの修理販売を個人で行っていた、現実のつげからの連想で設定されたシーンだろう。だが、私見では、つげにとってのカメラは、写真を撮ることよりも機械としてのそれに重点が置かれていた。そこが、映画の中の李と違う点だと思う。