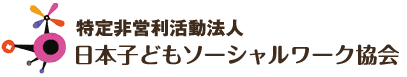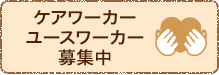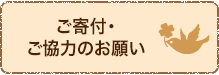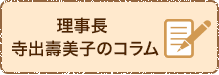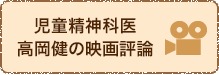日常の中の小さな非日常:「僕の中に咲く花火」
Vol.108 更新:2025年8月29日
▼腑に落ちる映画というものがある。「僕の中に咲く花火」(清水友翔監督)は、そういう映画だ。率直にそう思った。私の住む地域(岐阜)の風景が舞台に取り入れられているからでは必ずしもない。そうではなく、秀作によくみられる破調でもなければ、凡作によくある予定調和でもないところが、腑に落ちるのだ。
▼小学生の稔は、教室に車で迎えに来た父親とともに建物の中へ入る。その建物は病院で、稔の母はそこで亡くなり、建物は後に廃墟と化した。高校生になった稔(安倍伊織)は無免許運転で後輩の女生徒とともに元病院へ向かい侵入する。一方、田舎町の稔の家には、老いた祖母、接待と称し遅くまで帰宅しない父親(加藤雅也)、不登校で部屋へ引きこもる妹の鈴(角心菜)が暮らしている。稔は死後の世界を知るためもあってドラッグを試すが吐いてしまい、ちょうど帰省していた年上の女=朱里(葵うたの)に呆れられる。朱里と花火を見た夜に抱きあうシーンを挟んで、妹の自死と父の再婚が描かれる――。
▼このような展開と中味を支える構造を問われれば、すぐに二つ挙げることができる。一つは、個々の画面の九割以上が、やや斜めに傾いた配置で構成されているという点だ。人物でも物体でもいいが、ほとんどが画面の枠から微妙な角度を保って撮られている。それによって、この映画の描く世界が脆く、変化の方向も見かけ上は偶然に左右されることが暗示されている。だから、観客は押しつけがましい解釈を要求されず、どこかで自分の小さな体験と重ね合わせられるようになる。
▼もう一つは、家族間のやり取りの科白の中で、「そうか」という相槌が、関係の崩壊を期せずして食い止め中和する形で用いられているという点だ。「お前、どこへ行ってたんだ!」「花火…」「そうか、花火は楽しかったか」といった具合である。ちなみに、妹に対する稔の言葉つまり「みんな鈴に学校へ行ってほしいと思っている」の繰り返しが彼女の自死を惹起するのだが、それでも妹が「お兄ちゃん、ありがとう」と言い遺すのは、知らないうちに稔が「そうか」という相槌を挟んでいるからに違いない。
▼さらに附記することもできる。廃墟の病院へ同行した後輩の女生徒は、表情一つ変えない。他方、ドラッグを吐いてTシャツに染みをつけたまま朱里に連れられて入ったオデン屋で、オデン屋の親父から着替えに自分のシャツを貸された稔が戸惑うシーンがある。それを見た朱里は「自分のゲロより親父のシャツのほうが汚いってさ」と大笑いする。こういう年下と年上の女性の対比は、本質的にこの作品を青春映画たらしめている要素だ。
▼なお、まったくの蛇足だが、この冴えないタイトルだけは何とかならないものかと思った。しかし、よく考えてみると花火は日常の中の小さな非日常の象徴だし、もっと穿った読みをすれば、一見すると冴えないタイトルは、それを裏切る豊かな内容とのコントラストを狙ったがゆえなのかもしれないという気さえしてくる。