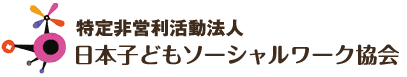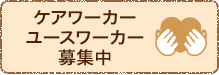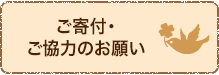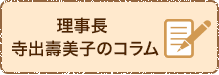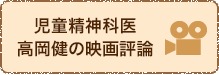日常とドラマの混淆:「うしろから撮るな」
Vol.105 更新:2025年5月5日
▼シリアスな振りをしているだけで、実際は腑抜けたホームビデオでしかないドキュメンタリーが評判になる昨今、「うしろから撮るな」(中村結実監督)には最初から最後まで引き込まれ、思わず眼を凝らして見てしまった。名脇役として知られ70年もの長きにわたって活躍した俳優織本順吉の晩年を追った作品で、監督は織本の長女だという。
▼やや冷たい言い方になるが、どんな場合でも実の家族を商業映画作品として撮影するには、撮る家族成員と撮られる家族成員との間に跳び越えがたいほどの距離が介在していることが、必須条件だと思う。この作品も例外ではない。25年間、織本と妻子は別居していた。妻もかつては俳優を目指していたが、織本を支えるため断念し、神戸の実家でパン屋を営みながら娘たちを育てた。その間、織本は、仕送りすら全くしなかった。妻子が織本を恨んでも当然だが、ここまでは未だ跳び越えがたい距離とまではいえない。
▼映画では、織本は草木の生い茂る家に妻は介護のために住み、そこへカメラを持った長女が訪れる。映画を観ただけではよくわからなかったが、この広い敷地に建つ家の場所は那須で、その目の前の土地は織本の女と思われる人の名義になっており、行く先々で織本の女が立ち回り、逆に誰も知り合いのいない土地で妻は何一つ収入の方策もなかったと、中村結実の著書『ジツゴト』には記されている。ここにまで至ると、織本と妻子とのあいだの距離は確実に跳び越えがたくなっているといってよい。
▼織本は、糖尿病の悪化に加え、だんだんセリフを忘れるようになる。「セリフは忘れないと、新しく覚えられないんだよ」と言いながら、NGの数は10回以上にも及ぶようになる。長いセリフを提供されて喜んだものの覚えられず、ついに俳優人生初の降板を余儀なくされる。眠るとセリフを忘れてしまうのが恐怖なのか、夜中の2時に起きて「気持ちの準備があるからもう着替える」と話すシーンには織本自身のプライドが見え隠れする。こうなると、織本固有の用語であるらしい「ドラマ」と「日常」の双方が、混淆した様相を呈するかのようだ。なお、入院ベッドの中で「中国に行かなきゃ」と話すシーンだけはよくわからなかったが、これは映画「MISHIMA」の海外での公開後に、中国へオーディションにきてほしいという話があったことと関連しているらしい(中村結実・前掲書)。
▼映画は、闘病や疑似的な家族愛や認知症の医療などを描こうとはしない。(主治医に対する織本の「医者ごときが」という言葉はあるが。)そういうありきたりで、おせっかいな啓発が挟まれていないところが、語弊を恐れず言えば何ともすがすがしい。この映画の出来上がりを見せられた織本は、「すごいドキュメンタリーだ」「お前だからできたんだ」「苦しんだが、ありがとう」「どれだけ嬉しかったか」と語る。形式だけの上映許可を得るための会話を超えた中味が、ここにはある。父娘の間の跳び越えがたい距離が、一挙に縮まったのではないか。あるいは、織本は最後まで俳優だったということか。