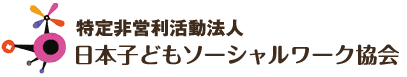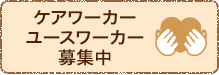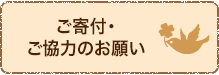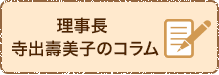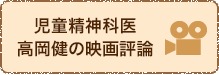その国では育ちたくない:「イロイロ ぬくもりの記憶」
Vol.7 更新:2015年2月5日
▼英国に住む人々に対して、シンガポールのイメージについて尋ねると、即座に警察国家(ポリス・ステート)という答えが返ってくる。旧・宗主国の国民が偉そうなことをと言われればそれまでだが(また、日本もシンガポールへ侵攻したことがあるから同様だが)、それでもシンガポールの異様さは、観光客でさえ感じとることができるはずだ。たとえば、街を汚したら罰金という貼り紙が、あちこちに見られる。(もっとも、日本でも、路上喫煙で罰金という貼り紙が、とみに目立つようになっているが。)
▼シンガポールの独裁政権は、自国の文化を不毛にすると闡明して、クリーンな国土をつくりあげてきた。だから、その国ですぐれた映画が撮影されるなどとは、誰もが思ってもいなかった。だが、「イロイロ ぬくもりの記憶」(アンソニー・チェン監督)は、なかなかいいのではないか。
▼アジア経済危機の1997年。一人っ子ジャールーの両親は共働き。そこにメイド(ドメスティック・ワーカー)として雇われたフィリピン人女性テレサは、ジャールーの部屋に住み込む。一方、母親は第二子を妊娠し、父親は失業を余儀なくされる。そのような中で、ジャールーは次第にテレサに打ち解けるようになるが、一家の家計は車を売らねばならないまでに悪化し、テレサは解雇され帰国する。別れの車の中で、テレサから思い出を切り取るため、ジャールーは鋏を手にする――。
▼宗教独裁の国=イランで、子どもが主演する映画が粒ぞろいであるのと、同じなのだろう。資本主義陣営の独裁国家=シンガポールで優れた映画がつくられるためには、子どもを中心に据えるしかなかった。それにしても、画面に挟み込まれる学校での体罰、喫煙者であるとの濡れ衣を着せられただけで解雇されそうになるテレサ、そして高層階からの自殺といったシーンを見ると、その国には住みたくない、その国では育ちたくないという気持ちにさせられる。(ただし、いまや日本も同様だが。)
▼ジャールーがテレサに「ぬくもり」を感じ、それを記憶に残したいと願う筋立ては、ほんとうは美談とは言えない。何よりも、母親とのあいだに愛着が成立しにくく、むしろドメスティック・ワーカーとのあいだに愛着が成立しやすいという社会は、そうとう歪んでいるのではないか。そこを告発するのではなく、巧みに隠しながら、鈍感な観客には美談であるかのように見せつける手腕を、若き監督は十二分に発揮した。
▼この手腕を支えている主要なファクターは、おそらく、画面を短時間で切り替えながら次々と前進させる、てらいのない編集なのだろう。若き監督は、旧・宗主国の国立テレビスクールで映画を学んだらしい。シンガポールで映画を志す若手監督のうち、どのくらいの割合が英国へ渡るのかは知らない。だが、渡英なしでは、この編集手法の獲得は困難であっただろうことも、想像に難くない。