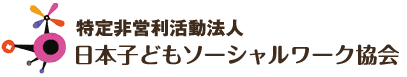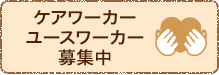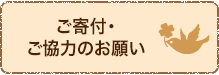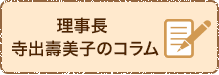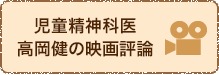闘う労組書記長:「私はモーリーン・カーニー」(+2023年ベスト5)
Vol.90 更新:2023年12月17日
▼労働組合が登場する社会派映画といえば、日本なら「沈まぬ太陽」あたりが真っ先に頭に浮かぶ。あの映画では、大手航空会社の労組員が懲罰的に仕事を与えられず、ただ抽斗に入れた栄光の活動家時代の集合写真を手でなぜることによってのみ、一日をやり過ごす姿が描かれていた。かたや、現代フランスの原子力発電企業ではどうなのか。そこを描いた作品が「私はモーリーン・カーニー」(ジャン=ポール・サロメ監督)だ。
▼原発企業アレバの労組女性書記長であるモーリーン・カーニー(イザベル・ユペール)は、フランス国内のみならず、ハンガリーの原発における首切りを解決するためにも闘っていた。モーリーンは、アレバの女性社長アンヌと直に話が出来る間柄だったが、サルコジはアンヌを解任して無能なウルセルという男性に社長を交代させた。その頃、アルバには、フィンランドにおける発電所建設の遅れにより、巨額の違約金が発生していた。
▼一方で、フランス電力公社(EDF)は、アレバをつぶし、中国広核集団と提携しようと画策していた。この動きを察知したモーリーンは、アレバの労働者5万人の雇用を守るため、中国に原発を売り渡すことに反対する。そういう中、彼女は自宅で何者かに襲われ、椅子に縛られて、ナイフの柄を膣に刺されてしまう。しかし、憲兵隊(地方警察)はモーリーンの自作自演だとして、逆に虚偽の告発をした罪で起訴し、彼女は一審で有罪にされてしまう――。
▼これが実話に基づくというから驚きだ。巨悪と対峙するモーリーンを演じるユペールは、いつも颯爽としているけれど、不屈という言葉が当てはまるわけではない。それでも、日本の連合などのダラ幹連中には望むべくもないような、孤立しながらも負けない闘いがどういうものかを、感心するほどうまく演じていた。
▼ただし、モーリーンと共に行動する労組員の姿は、先述のハンガリー原発の労働者および二審判決の場面以外には、ほとんど描かれていない。逆に、モーリーンの被害が自作自演だと決めつけられる根拠は、若い頃の彼女がレイプの被害者だったからだという捜査側の解釈が前面に押し出されている。ある種の言いがかりなのだが、こういうまことしやかな解釈さえもが通用しそうになるところが現在の社会病理だろう。そして、社会病理が前面に押し出されると、集団の闘いは簡単に後景へ退いてしまう。それもまた社会病理だ。
▼原題は「LA SYNDICALISTE」。フランス語はよくわからないが、モーリーンがアナルコ・サンジカリストだとは思えないから、これは労組活動家というほどの意味だろう。
▼付記:2023年のベスト5(本欄で取り上げたもの以外)は次の通り。「コンパートメントNo.6」「グッドバイ、バッドマガジンズ」、「放課後アングラーライフ」、「君は行く先を知らない」、「映画(窒息)」。例によって、あくまで私見だから、目くじらを立てないようお願いする。