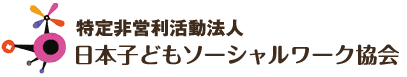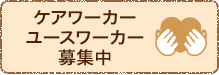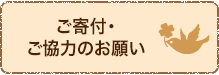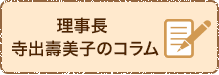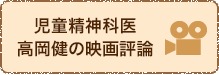逆回しのロードムービー:「658km、陽子の旅」
Vol.87 更新:2023年10月1日
▼未だ無名の若者が、未知の目的地へ向かう過程で、少しずつ自己を発見し確認していくところにロードムービーの基本型があるとすれば、その過程を中年期以降に逆回しに辿ることは、はたして可能なのか。「658km、陽子の旅」(熊切和嘉監督)は、そのことを主題に据えた映画だ。40歳代で独身の陽子(菊地凛子)は、ほとんど誰ともコミュニケーションのない生活を、東京で送っていた。彼女の部屋に従兄がやってきて、陽子の父の死を知らせる。陽子の携帯が壊れていてつながらなかったため、直接、知らせに来たのだった。
▼ただちに陽子は従兄一家の車に乗せられ、故郷へと向かう。しかし、途中のサービスエリアで従兄一家からはぐれてしまった陽子の携帯は壊れたままで、所持金は二千数百円しかなく、ヒッチハイクでの帰郷を余儀なくされる。シングルマザーの軽乗用車、ライターだという男の乗用車、老夫婦の軽トラック、被災地に定住したという関西出身の女性の車、そして子を助手席に座らせた男が運転する車などにのせてもらい、果てはバイクの後ろにまたがって、葬儀の営まれる青森(車を止めるためのスケッチブックには林檎とともに岩木山らしい絵が描かれていたから正確には弘前なのだろう)の実家を目指す――。
▼逆回しに辿るとは、来し方を振り返ることとは異なる。だからカットバックは要らないし、回想も最小限で、しかもそれは抽象化された幻影でよい。そういうわけで、この映画には、かつて確執のあったらしい父親は、幻影として登場するだけだ。ちなみに、どんな確執だったかは、終わり近くの説明的な長台詞により示唆されるが、「しょうもない話」と陽子自身が断っているように、特別に劇的な話ではない。劇的である必要性はないからだ。(その意味では、ライターの男に性交を余儀なくされるシーンは不要だし、ついでに言うと、いまや定番と化した震災ボランティアから被災地への定住といったエピソードも不要だろう。)
▼一般にロードムービーでは、旅の途中で出会う人物の描写が、一つの生命線だ。この映画でも、最初に陽子を同乗させるシングルマザーの黒沢あすか、ほとんど車が止まらないパーキングエリアで出会う見上愛が、こういう人っているよなと思わせ、秀逸だった。そして何よりも、かつての「天使の恍惚」で記憶に刻印されている吉沢健の演じる老人が、とまどいながら陽子と握手をし、妻の風吹ジュンから皮肉でなく「よかったねえ」と言われて照れるシーンには、思わず頬が緩んだ。
▼ところで、この映画の最初と最後には、GSのヒット曲であり、私も好きな「亜麻色の髪の乙女」が使われている。陽子の父がよく歌っていたという設定だ。現在42歳の陽子が家を出たのは18歳で、そのとき父は現在の陽子と同じ年齢だったとされているので、この映画の脚本がTSUTAYA CREATORS’ PROGRAMで受賞した2019年を「現在」と仮定して逆算すれば、陽子の父の生年は1953年だ。調べると「亜麻色…」の発売は1968年だから、父は15歳の頃に聴いたビレッジシンガーズの歌を、ずっと口ずさんでいたことになる。