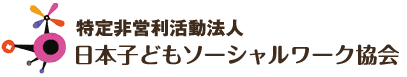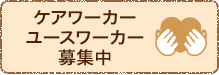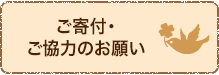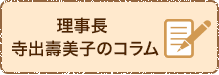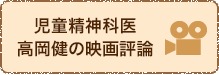主人公は民衆:「生きるLIVING」
Vol.84 更新:2023年6月17日
▼トルストイの『イワン・イリッチの死』を翻案してつくられたといわれる黒澤明の「生きる」を、さらにカズオ・イシグロが脚本化して生まれた評判作が、「生きるLIVING」(オリヴァー・ハーマナス監督)だ。
▼黒澤版「生きる」は1952年公開だから私はビデオでしか観たことがないが、いわば後の難病・闘病ものの原点のような作品だ。しかも、押しつけがましさが何とも不快というしかない今日の難病・闘病ものの映画とは違って、重厚な説得力に貫かれた作品だった。あえて全くの私見を述べるが、重厚な説得力を感じる理由は、胃がんに侵された市役所課長がほんとうの主人公ではなく、彼が死の間際に民衆のために実現した児童公園の建設を要望していた市井の女性たちこそが、ほんとうの主人公だったからだと思う
▼ハーマナス版「生きるLIVING」は、ほぼ忠実に黒澤版をなぞっている。時代は黒澤版公開の翌年である1953年。ハーマナス版の市民課長ウィリアムズ(ビル・ナイ)も黒澤版の市民課長渡辺(志村喬)も、ともに胃がんに侵されている。ウィリアムズは貯金の半分を持ち出し劇作家と遊び、渡辺は当時の金額で5万円を小説家とともに費消する。そのときに歌う曲は、ウィリアムズが「ナナカマドの木」で、渡辺が「ゴンドラの唄」。ウィリアムズのあだ名はゾンビで渡辺のあだ名はミイラ。そして、ウィリアムズが元市職員の若い女性と「フォートナム」での食事後にUFOキャッチャーで狙うのはウサギのぬいぐるみで、渡辺がレストランで受け取るのは女性が賃労働でつくるゼンマイ仕掛けのウサギの人形――。
▼では、民衆の描き方はどうか。両作品における民衆とは、児童公園整備の陳情に訪れ各課をたらい回しにされる女性たちだ。ハーマナス版の民衆は一見した限りでは意識高い系の女性たちかと思ってしまうが、劣悪な地区の公園で子どもたちを遊ばせざるをえない地元の母親たちというシチュエーションを念頭に置くと、敗戦国日本の民衆である貧しい母親たちとかわらない。一方、市役所の職員たちは仕事をせずに時間をつぶし、住民の福利など端から考えない(もちろん現在ではイギリスも日本もかなり変わり住民の利害を重視するようになっているが)。そのような姿を体現していた課長が、死を前にしてはじめて民衆のために仕事をする。そして、それを民衆である母親たちは、彼の死後になっても決して忘れない。民衆が主人公とは、そういう意味だ。
▼「生きるLIVING」が、黒澤の「生きる」と同程度に、誰がみてもエッジの利いた作品に仕上がっているのに対し、昨今の難病・闘病ものの多くが、自己愛のかたまりのような腑抜けた印象しか与えないのは、個人的な体験であるはずの病気を観客に共有するよう強制するからだ。ところが「生きるLIVINNG」は黒澤作品へのリスペクトに貫かれているぶんだけ、個人的な罹病の体験が普遍化しうる媒介として、民衆である女性たちを描き込んでいる。つまり、ほんとうのリスペクトにあふれているのである。