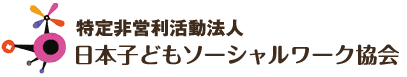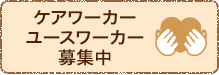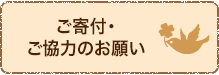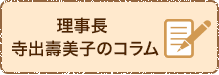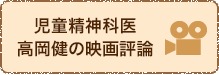被害−加害図式を相対化する無国籍映画:「赦し」
Vol.83 更新:2023年5月21日
▼昨今の日本の刑事(少年)裁判を巡っては、被害者や被害者家族の立場に同一化して、正義の名の下に加害者や加害者家族を糾弾する論調が跡を絶たない。加害者が少年であったり精神障害者であったりした場合は特にそうで、弱者でもある加害者は、元々不安定であった社会を安定化させるための生贄でもあるかのような役目を担わされる。
▼被害者−加害者のあいだに何らかの関係性が存在した場合には、実は加害者が被害者であったり、逆に被害者が加害者であったりすることも少なくはないが、そういう事情はほとんど伏せられる。また、時には加害者と加害者家族とのあいだに関係の歪みがありうるのと同程度に、被害者と被害者家族とのあいだに断絶が存在していたということもありうる。そういう場合であれば、被害者家族は断絶がなかったかのように振舞うために、加害者や加害者家族に対する糾弾のトーンをあげつづけねばならない。こうなると加害者の更生などは、決まり文句のような御題目としてしか考慮されないことになる。
▼かかる状況を、映画表現において突破することができるのか。この難しい問いに答えようとした作品が「赦し」(アンシェル・チョウハン監督)だ。7年前に樋口(尚玄)と澄子(MEGUMI)夫妻の娘が、高校の同級生だった福田夏奈(松浦りょう)によって殺害された。事件後、澄子は離婚し、グループカウンセリングで知り合った男性と再婚する。一方、樋口は酒浸りの生活を送っている。
▼そこへ、裁判所から再審が開始されるとの連絡が舞い込む。再審では、加害者が少年であったことが7年前に軽視されていたという点が争点となる見込みだ。樋口は澄子を誘い再び裁判所で厳罰を訴えるが、夏奈がいじめの被害を受けていたこと、夏奈の母親は事件後に賠償金を支払ったあと亡くなっていることなどを聞かされ、二人とも裁判から降りる――。
▼この映画は、愛知県で起こった少年事件からインスピレーションを得て構想されたというが、私などが知る限りでは実際の事件とは懸け離れているし、裁判の展開そのものも少なくとも日本ではありえない造りだ。在日インド人監督が撮った作品だからなのか、そういう意味では無国籍映画とでもいうしかない。しかし、無国籍映画という形でしか描くことができないのが、今の日本における少年裁判の現実だともいいうる。つまり、無国籍化することで、はじめて被害者−加害者の図式を相対化しつつ考えることが可能になるということだ。
▼ところで、映画の中の夏奈の語りは独特だ。ほとんど表情を変えずに、抑揚を取り去った早口で、自分には許される資格はないが、出所したなら今後は同じような立場の少年が犯罪に手を染めないための活動をしたいと話す。そして、それが本心なのか建前を述べているだけなのか、観客にはわからない仕組みになっている。この語りもまた、厳罰−更生間の対立の、無国籍化による相対化といっていいだろう。いいかえるなら、無国籍化によってしか描くことのできない現実が、日本の裁判状況が陥りつつある袋小路を象徴している。