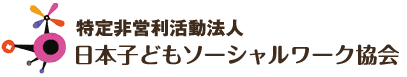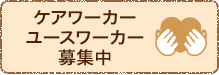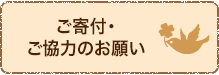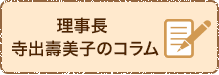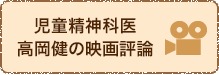定点としての工場群の描写:「リバーズ・エッジ」
Vol.38 更新:2018年4月2日
▼1990年代になると、それまで日本の第二次産業社会を支えていた工場群の多くが、次第に操業を停止していった。一部の工場は残るが、未だ「工場夜景見学ツァー」といった愛され方(?)は生まれず、工場の傍の汚れた川原には、セイタカアワダチソウが茂るばかりだった。そういう時代に一瞬だけ成立していた、高校生たちの交錯する心と行動を描きだした漫画が、岡崎京子の『リバーズ・エッジ』だ。その漫画が、行定勲監督の手によって映画化された。
▼ストーリーは、ほぼ原作を踏襲している。「若草ハルナ」(二階堂ふみ)は、「観音崎」(上杉柊平)という同級生とつきあっていた。観音崎は、ゲイの「山田」(吉沢亮)をいじめ、夜中に放置した。その山田を、ハルナは助けた。山田はハルナを川原に案内し、白骨化した死体を見せる。
▼脇を固める若手女優の2人(SUMIREと土居志央梨)が、印象に残る。SUMIREの演じる「こずえ」は、高校生ながら売れっ子モデルで、かつ摂食障害のため食べ吐きを繰り返している。一方、土居の演じる「ルミ」は、教室で化粧をしながら、気怠そうに「私、観音崎君、嫌い」とつぶやくが、その観音崎との性交で妊娠してしまう。
▼こういったストーリー展開の中に、工場群の遠景が挟み込まれている。もし、工場群が描かれていなければ、才覚ある女性監督の映画や、才気あふれるトランス・ジェンダーの監督による、単なるビジュアル映画と同質の作品へと、陥っていたかもしれない。(同じく岡崎原作の映画「へルタースケルター」は、その一例だ。)
▼漫画の中で、ハルナらを<図>として浮かびあがらせたのは、<地>としての工場風景だった。このような対比により、ハルナ・こずえ・ルミら女子高校生の未来の姿を、示唆することが可能になった。彼女らは、命を失わない限り、工場群の操業停止が一段落した後、過去を忘れたかのように、新たな生を営んでいるに違いない。(もちろん、完全に忘れ去ることはできないのだが。)だから、映画化に際して、工場群の描写を省略することは、絶対にできなかった。
▼映画には、原作にはないインタヴュー場面(俳優への抜き打ちインタヴュー)が、随所に含まれている。これらの場面に対する評価はさまざまだろうが、どちらかというと私は肯定的だ。工場群の遠景が定点になっていて、そこから観測された考えや気持ちが、語られているように映るからだ。通常よりも横縦比の小さい画面(スタンダード・サイズというそうだが)の効果とともに、工場群との対比があるからこそ、不安定になりかねないインタヴュー場面の安定が、確保されたのだろう。それにしても、現実の工場群が次々と操業を停止し、「工場夜景見学ツアー」にとってかわられるとき、何がハルナらの新しい定点になるのだろうか。