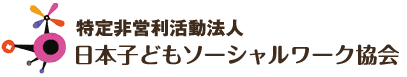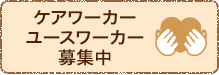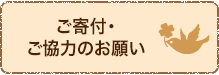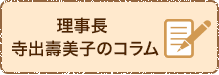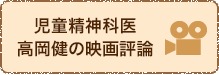評判のジョージア映画:「花咲くころ」
Vol.37 更新:2018年2月28日
▼「花咲くころ」(ナナ・エクフティミシュヴィリ、ジモン・グロス共同監督)が、評判を呼んでいる。旧ソ連からの独立を果たしたとはいえ、内戦の余波が続き、アブハジア戦争へと至る直前の状況を背景に、14歳の少女たちの姿を描いた作品だ。ただし、内戦や民族戦争そのものは、セリフの端々にのぼるだけで、正面切って描かれることはない。2人の少女に関係して映画が描くのは、ピストルと暴力的な結婚だ。
▼モスクワへ赴く若者ラドが、少女ナティア(マリアム・ボケリア=撮影当時は新人)に、身を守るためのピストルを贈る。ナティアは、少女エカ(リカ・バブルアニ=撮影当時は新人)に、彼女を苛める少年コプラを脅すため、ピストルを渡す。しかし、エカは、コプラが他の少年たちのグループから殴られるのを見て、ピストルを少年グループに突きつけ、逆にコプラを救う。
▼一方、ナティアは、不良のコテによって略奪婚を強いられる。結婚後、誕生日を祝ってもらうことさえなくなったナティアは、彼女とエカと祖母の3人だけで、自らの誕生日会を開く。そこへ戻ってきたラドは、嫉妬したコテに刺されて死ぬ。復讐へ向かうナティアから、エカはピストルを取り上げ、池に捨てる――。
▼だが、このようなストーリーの傍に挟み込まれた、いくつかの小さなエピソードの方が、私の眼には焼き付いて残った。一つは、ペンキが剥げかけたエカの家の一室に少女たちが集まり、隠れてタバコを吸う場面だ。少しとげとげしさが混じりながらも屈託のない会話が弾むが、母親がやってくると、彼女たちはあわててタバコの火を消し、窓を開ける。
▼もう一つは、いかにも旧ソ連的な女教師の強圧的教育に反発した少女たちが、同じ学校の少年たちとともに教室から飛び出し、メリーゴーランド風の乗り物の上で、歓声をあげる場面だ。私の見間違いかもしれないが、乗り物には、ところどころ錆が浮いていた。これらの場面により、「花咲くころ」は、ジョージアの映画から世界の若者の映画へと、軽々と越境し飛躍することができた。
▼それにしても、私などの素人にとって、ジョージア(グルジア)は、未知の部分があまりにも多い。そもそもスターリンの出生地らしいことは知っていたが、たしかスターリンは、ロシア革命直後にグルジアの共産党員を「民族主義的逸脱」と非難し、大ロシアへの統合を画策したはずだ。その頃、レーニンの病は進行し、トロツキーもグルジア問題にかかわることを避けた。こういった、当初からの曖昧さが、旧ソ連の崩壊を契機とする民族国家問題の噴出を、容易にしたことだけは確かだ。
▼欧米諸国は、自らの利害のみに立脚して、噴出する民族国家問題を、これまでと同様、これからも恣意的に扱おうとするに違いない。だが、世界へ軽々と越境する若者らがいる限り、先進諸国の恣意性は、確実に崩されていくだろう。