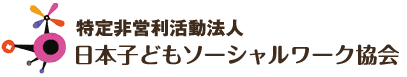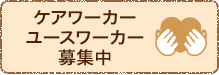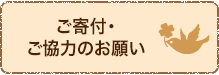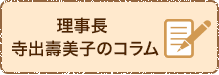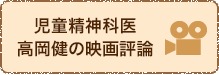巨匠の遺作:「残像」
Vol.34 更新:2017年9月4日
▼アンジェイ・ワイダ監督の遺作「残像」は、ポーランドのウニズム絵画に対し、社会主義リアリズムを強要する体制が、容赦なく弾圧する姿を描いていた。左右の全体主義から、一貫して人間の表現を守ろうとしたワイダの、遺作にふさわしい主題だったといってよい。
▼もっとも、主題以上に、遺作にふさわしいと私が感じたのは、ウニズムの画家・理論家でありウッチ造形大学の教授でもあるストゥシェミンスキ(ボグスワフ・リンダ)の抵抗を、ロマン(トマシュ・ヴウォソク)とハンナ(ゾフィア・ヴィフワチ)という男女学生が、物質的に支えようとする、いくつかの場面だ。職を追われ、食糧の配給を手にすることも出来なくなったストゥシェミンスキは、看板描きの仕事でさえ、パンのために引き受けようとする。それでも、2人の学生は、ストゥシェミンスキを慕う。そればかりか、当局による監視下であるにもかかわらず、彼の「視覚理論」を口述筆記するためにタイプライターを盗み、また、なけなしの伝手で彼に手仕事を斡旋しようとする。
▼抵抗も闘争も、1人ではできない。いいかえるなら、1人の理論家の背後には、必ず無名の若者たちがいる。そのことを、ワイダは、忘れずに描いてくれた。
▼ところで、「残像」より1つ前のワイダの作品は、「ワレサ 連帯の男」だった。ワレサが率いた「連帯」が、グダンスク造船所から世界に向けて、新しい社会の幕開けを告げるかもしれない闘いを発信したことは、まぎれもない歴史的事実だった。だからこそ、その後のワレサとの対立にもかかわらず、ワイダは「ワレサ 連帯の男」を撮ったのだろう。しかし、その時点ですでに、「連帯」からはじまる新しい流れは、単なるナショナリズムに回収されてしまうおそれを、常に伴っていた。
▼分裂を重ねた元「連帯」から、右派グループを率いて「法と正義」を結成した双子のカチンスキ兄弟のうち、大統領にまでのぼりつめた弟レフは、ワイダも映画で描いたカチンの森事件から70周年の追悼式典へ向かう専用機墜落により、死亡した。しかし、兄ヤロスワフを党首に擁する「法と正義」は、2015年10月のポーランド総選挙に勝利し、政権の座についた。政権交代後すぐに、「法と正義」は憲法裁判所を支持者で固めるとともに、同裁判所の決定に必要な判事の同意数を、過半数から3分の2へと引き上げた。これにより、「法と正義」による立法に対しての違憲判断が、事実上、不可能になったといわれる。
▼ヤロスワフ・カチンスキは、ハンガリーの右派=オルバンに匹敵するほどの、保守ナショナリストとして位置づけられている。反イスラムを明言し、「移民が病気や寄生虫をポーランドに持ち込む」とまで発言している。また、強いNATOが必要と主張しながら、EU懐疑派の立場を崩さないとも報道されている。ほんとうのところはどうなのか。「連帯」は、結局、ナショナリストの運動に過ぎなかったのか。巨匠の考えを、映像をとおして知りたいところだが、いまや不可能になった。